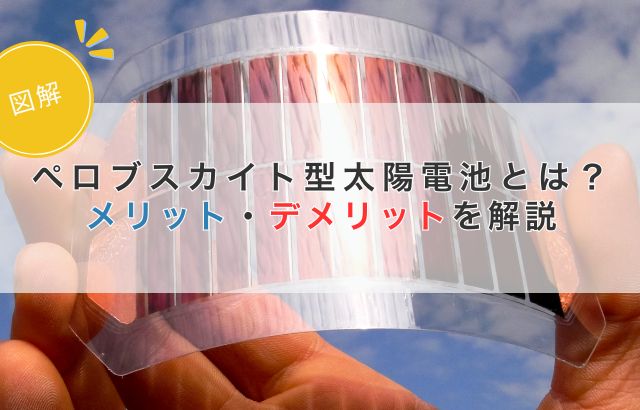太陽光発電と蓄電池の導入で元が取れない?原因や対策方法を解説

太陽光発電と蓄電池は、それぞれ再生可能エネルギーを有効に活用できる設備です。電気代の高騰傾向が続く今、併せて導入する企業も増えています。
しかし、太陽光発電と蓄電池の導入にはまとまった初期費用がかかるため、「果たして元がと取れるのか?」と疑問を抱く方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本コラムでは、太陽光発電と蓄電池の導入で元が取れない原因と、元を取るための具体的な対策方法を解説します。
また、太陽光発電の仕組みや役割、メリット・デメリットなどから詳しく理解したい方は、下記記事も参考にしてみてください。
太陽光発電と蓄電池の導入で本当に元が取れないのか?
産業用の太陽光発電と蓄電池において「元が取れる」といえる状態とは、両設備の導入によって得られる経済的利益が、導入にかかる初期費用を上回る状態です。
一般的には、メーカーによって設備の修理・交換が可能な保証期間内に初期費用を回収できるだけの経済的利益が得られることを指します。
メーカーの保証期間は、「メーカーが設備の品質を保証する期間」です。
その期間内に初期費用を回収できないような場合は、設備や設置環境などに何かしらの原因があると考えられるため、早めに原因を見つけて対処する必要があります。
太陽光発電と蓄電池を導入して元が取れない時に考えられる原因
ここでは、太陽光発電と蓄電池の導入で元が取れない場合に考えられる原因を紹介します。原因を知ることで対処方法が見えてくるため、しっかりと確認しておきましょう。
必要以上に初期費用をかけすぎている
太陽光発電や蓄電池の導入に対して必要以上に費用をかけすぎてしまうと、当然ながらその回収にも時間がかかったり、元が取れなかったりすることもありえるでしょう。
そのため、必要以上の高性能・大容量の製品を選んでいたり、太陽電池モジュールや蓄電池の容量が多すぎたりするケースでは、「経済的利益は上がっているものの、元が取れない」といった状況に陥るでしょう。
売電に頼り過ぎている
太陽光発電によって得られた余剰電力は、電力会社に販売することが可能です。
この売電収入を、太陽光発電や蓄電池の元を取るための大きな要素と捉えている企業も少なくないでしょう。
しかし、売電価格は契約年度ごとに変動します。FIT制度による電力買取単価を見てみると、制度がスタートした2012年度は10kW以上で40円でしたが、年々下落し、2025年度には11.5円になることが決まっています。
こうした状況下では、売電重視で元を取ろうとするのは難しいといえるでしょう。
参考:資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2024年度以降)」
参考:資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2012年度~2023年度)」
メンテナンス不足により発電量が落ちている
太陽電池モジュールの発電量が低下する原因のひとつに、メンテナンス不足が挙げられます。
特に屋外に設置される太陽電池モジュールでは表面に汚れや埃、鳥のフンなどがつきやすく、掃除を怠ると発電量がどんどん低下してしまいます。
太陽光発電と蓄電池を上手く連携できていない
太陽光発電と蓄電池の両方を導入していても、互換性のない製品を選んでしまっている場合には上手く連携できません。
太陽光発電では、先に太陽光発電設備だけを設置していたところに、あとから追加で蓄電池を導入するケースもよく見られます。
特にセット導入でない場合は、今一度互換性の有無を確認してみるとよいでしょう。
補助金や減税を上手く活用できていない
太陽光発電や蓄電池の導入は、カーボンニュートラルの実現に向けて国や自治体が積極的に普及を推進している事業です。
そのため、さまざまな補助金や税制優遇が用意されています。
そうした補助金や減税の活用も、太陽光発電や蓄電池の導入で元がとれるかどうかを左右する要因のひとつです。上手く活用できなければ、元が取れない可能性が高まってしまうでしょう。
設置場所の発電ポテンシャルが低い
太陽光発電は、どこに設置しても同じように能力を発揮する設備ではありません。設置に向かない場所が存在するのが事実です。
太陽光発電の設置場所が以下のような条件に当てはまる場合は、発電効率の低さから元が取れない可能性があります。
- 日照時間が少ない
- 日差しを遮るものがある
- 十分に太陽電池モジュールを設置できる広さがない
- 海が近く塩害のおそれがある
- 雪が多い
そもそもシミュレーションページが上手くできていない
太陽光発電や蓄電池を導入する際には、事前に設置業者などにシミュレーションを依頼し、導入検討の参考にする企業が多いのではないでしょうか。
しかし、太陽光発電や蓄電池の導入・運用の効果は事例ごとに異なる上、算出するにはさまざまな要因を複雑に組み合わせて計算しなければなりません。
すべての業者がそれだけのスキルを持ち合わせているわけではないため、残念ながらシミュレーション結果自体に誤りがあるケースもあります。
太陽光発電と蓄電池で元を取るための具体的な方法とポイント
ここからは、前章で紹介した課題を基に、太陽光発電と蓄電池の導入・運用で元をとるための具体的な戦略を紹介します。
自社で対応可能かどうか検討してみましょう。
自社に合った太陽電池モジュールと蓄電池を選ぶ
太陽電池モジュールや蓄電池は、自社の消費電力量や売電目標、設置場所などに合わせて最適な製品を選ぶことが大切です。
例えば、工場やオフィスの屋根に広範囲にわたって設置する場合には、耐久性とコストを重視した太陽電池モジュール選びが求められます。
蓄電池選びでは、容量の選択が重要ポイントです。
自社に必要な容量を選ぶ際には、1日あたりに余る電力量(余剰電力量)や、災害時に必要となる電力量を基に、自社に最適な容量を算出するのがおすすめです。
売電だけに頼らず自家消費率を上げる
先に紹介したように、売電価格は年々下落しています。
加えて電気代の高騰傾向が続く昨今では、電気を自家消費することで電力会社から購入する電気量を抑えたほうがお得になるケースも多いでしょう。
発電量や消費電力量にもよりますが、売電から自家消費へと電気の活用方法をシフトするのもひとつの手です。
定期的なメンテナンスを怠らない
太陽電池モジュールを長く安定的に使うためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
汚れや埃は気づかないうちに溜まるもので、あまりに溜まってしまった場合には、清掃費用も高額になってしまいます。
一般的な汚れであれば、自社でも対応可能です。
まずは目視で大きな異常がないかを確認したあと、洗剤を使わず、水で流しながらモップなどで軽くこすり洗いします。
ただし、安全性や確実性を考慮すれば、専門業者に依頼するのが無難です。専門家でなければ気づけないような異常の早期発見にもつながります。
太陽光発電と蓄電池を連携して活用する
太陽光発電と蓄電池をしっかりと連携させながら活用すると、太陽光発電のメリットを拡大させられます。
例えば、貯めておいた電気を夜間や発電量の少ない悪天候時に自家消費すると、電気代の削減率を向上させられるでしょう。
国や地方自治体の事業者向け補助金・助成金を上手く活用する
2024年11月現在では、本年度に利用できる国の事業者向け補助金・助成金の公募はすべて終了していますが、来年度以降も同様の制度の維持と公募がある見込みです。
主なものには、以下のようなものが挙げられます。
- 「需要家主導型太陽光発電及び再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業」(経済産業省)
- 「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」(環境省)
地方自治体でも、独自の取り組みが見られます。一例として、東京都の補助金について以下記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
補助金・助成金の申請条件や必要書類はそれぞれ異なります。複雑な内容も多いため、申請手続きを代行する業者やメーカーに依頼するとスムーズでしょう。
参考:経済産業省 令和6年度予算「需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金」に係る補助事業者(執行団体)の公募について
参考:一般財団法人環境イノベーション情報機構 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)
専門の業者やメーカーに無料でシミュレーションをしてもらう
太陽光発電と蓄電池の導入効果をより正確に検討するためには、精度の高いシミュレーションが必要です。
当社でも、無料シミュレーションを実施していますので、お気軽にお試しください。
まとめ
太陽光発電と蓄電池の導入には大きな費用がかかりますが、戦略的に導入・運用することで元が取れることも期待できます。
太陽光発電と蓄電池を上手に併用することで、よりメリットを活かせるでしょう。
日本発祥のリープトンエナジーは、国内外で多くの太陽光発電の導入実績を誇る太陽電池モジュールメーカーです。
これまで積み上げてきた経験を活かし、精度の高いシミュレーションや太陽光発電の導入・運用をアドバイスいたします。
太陽光発電と蓄電池の導入をご検討中なら、ぜひ一度ご相談ください。
監修者

リープトンエナジーブログ編集部
”神戸発”太陽電池モジュールメーカー、リープトンエナジーが太陽光発電について易しく詳しく解説します。お問い合わせは、右上の「お問い合わせ」からお気軽にどうぞ。